「なんで1904年なの?」
職場の先輩が僕に問いかけてきました。
マイクロソフトのWindows版Excelで、セルの表示形式が「標準」のときに日付を入力すると謎の数字が出現しますよね。
例えば「2013/2/5」と入力すると41310という数字になりますが、これは1900年1月1日からの経過日数だそうです。
そしてこのシステムは、Excelのオプション設定で1904年1月1日から数えられるように切り替えることができます。
そこでさっきの質問が投げかけられたというわけです。
そういえばなんでだろう…。今まで考えたこともありません。
先輩は普通の人はスルーしてしまいがちな、どうでもいいようなことにも疑問を持つ好奇心旺盛な方で、僕はそれを一緒になって調べるのが好きです。
早速ネットで検索やで!
カチャカチャカチャ…ターン!!(エンターキーが取れんばかりの勢いで)
世の中は広いもので、自分たちが疑問に思うようなことは既に他の誰かがネットで質問していて、それに対する回答も別のジーニアスがきちんと用意してくれているものです。
Windows版より先に開発されたMac版Excelでは、1904年からの日付システムを採用しているので、互換性を保つための設定なのだそうです。
ではなぜ1904年かというと、1900年が閏年ではなかったという事実に関連する問題の発生を避けることを目的としているらしい。
つまり、初期のExcel開発段階で1900年からではなく1904年からにすることで、プログラムを簡単にすることが目的だったそうです。
なるほどのぅ、そういう深い事情があったわけか。
ん?
1900年が?閏年ではなかった?4で割り切れる年なのに?
そして発覚した衝撃の新事実。
閏年が4年に一度というのは絶対的な法則ではなかったのです。
なんと、4で割り切れる年であっても100で割り切れる年は閏年ではないというではないか。
つまり、1896年や1904年は閏年ですが、1900年は閏年ではないのです。
ところで2000年はどうだったか覚えていますか。
今話した法則に則ると閏年ではないはずですが、なぜかバッチリ閏年でした。
そう、更なる例外があるのです。
4で割り切れて、100でも割り切れる年であっても、400で割り切れる年は閏年とするそうです。
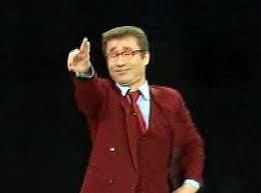
ややこしやー ややこしや
整理すると、閏年は基本的に4年に一度やってくると覚えておけばいいんだけど、ごく稀に例外がある。
2100年、2200年、2300年は閏年ではない。でも2400年は閏年。
まぁ、次にイレギュラーなパターンがやってくるのは2100年で、僕は確実に天に召されているからどうでもいいことです。
そもそも閏年が存在するのは1年の長さが365日5時間48分45秒強だからそのズレを修正するためにあるそうです。
では1秒の長さの定義ってなんだろう?
昔は地球の自転が基準になっていたらしい。
すなわち1日の1/24を1時間、さらにその1/60を1分、そのまた1/60を1秒という風に。これはとてもわかりやすい。
でも、これはけっこうズレがあるということがわかった。
より確かな基準として、次は地球の公転が基準になった。これもわかりやすい。
ただそれでもやっぱり結構ズレるらしいぞと。
どうしたもんかと。
そして1967年から採用された1秒の定義がこれ。
「セシウム133原子の基底状態の2つの超微細準位間の遷移に対応する放射の9,192,631,770周期の継続時間」
あぶぶぶぶぶ
難しすぎて震えてきます。
何かの呪文かなと思ったよ。
91億とかすごい数字。
何一つ理解できる要素がありません。深く考えると爆発してしまいそうなので追求しません。
これだけでも何だかとてもすごそうなんだけど、最近新聞でもっと正確な1秒を決めるための新基準が採用されるかもしれないという記事を見た。
136億年(だったかな?)に1秒しか誤差が生じないらしい。
すごいだす。
人類すごいだす。
ピテカントロプスになる日も近づいたかな。
それにしても世の中は知らないことばかり。
まだまだまだ盛りだくさんライフ!







